【読解力を作り出す】4)間違いだらけの「読解問題演習」
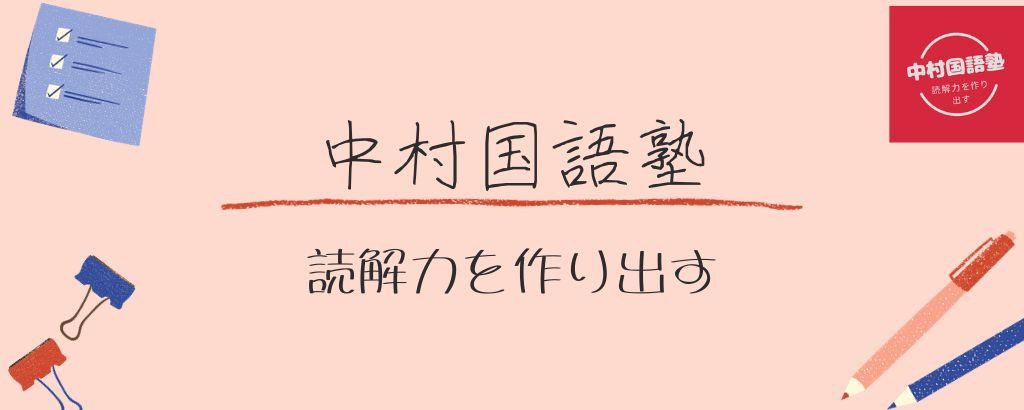
1)こんな問題練習になっていませんか?
小学5年生のA君は、私立中学合格を目指し、大手塾に通いながら日々勉強に励んでいます。
彼は決して国語が苦手というわけではありませんが、どちらかといえば算数や理科の方が好きで、興味を持って取り組んでいます。一方で国語の勉強に対しては、「できるだけ早く終わらせてしまいたい」という気持ちが強く、家での学習時間も自然と短くなりがちでした。
毎週の宿題として課されるのは、読解問題が2題と、漢字練習が5ページ分。漢字については、次の授業で確認テストが行われるため、A君も意識的に取り組んでいました。その成果もあって、漢字テストでは毎回ほぼ満点に近い点数を取ることができていました。
しかし、読解問題となると話は別です。宿題として、取り組むことは取り組むのですが、解答は埋めてあるものの、解き方はかなり雑。間違えた部分も、赤ペンで答えを書き写して終わり。なぜ間違えたのか、どのように考えれば正解にたどり着けたのか、などの振り返りがほとんどできていない状態でした。
そんな状態のまま迎えた組み分けテストでは、算数や理科に比べ、国語の成績が明らかに低迷。宿題は取り組んでいるし、授業もしっかり受けているはずなのに、国語の偏差値はむしろ下降傾向にありました。
この状況を見かねたA君のご家庭は、塾の先生に相談。「国語の宿題はちゃんとやっているのに、なぜか成績が伸びないんです」と訴えたところ、先生からの提案は「宿題の量を増やしてみましょうか」
そこで、新たに読解問題集を1冊用意し、これまでの宿題に加えて、毎週1題ずつ追加で取り組むことになりました。しかし、追加された問題にもA君はあまり気が乗らず、やはり「とりあえず解いて答えを書き写す」という作業的な取り組み方は変わらず。
そうこうしているうちに、算数の偏差値は50を大きく超えるほど伸びていたのに対し、国語はついに40を下回るまでに低下。(※偏差値は四谷大塚の組み分けテスト基準)
そして、ついにA君の口からこぼれたのは、
「国語やりたくない……」
という言葉でした。
国語の読解問題演習は、ご家庭で取り組む際になかなかの鬼門です。上記のような取り組みは、決して量的に見れば少ないわけではなく、漢字をしっかり取り組み、読解問題を3題も取り組むというのは、小学生にとって決して易しい課題ではないです。
でも、これをずっと続けていても、未来永劫、国語の成績が上がることは難しいように感じます。
では、どのように取り組めば、読解問題演習において、読解力が高まり、得点力が上がっていくのか、そのポイントをいくつかみてみましょう。
2)読解力のつく問題演習のためのチェックポイント
- 問題演習を行う際は、必ず「制限時間」を設定しよう
→制限時間のない問題練習は、ルールのないゲームのようなもので、取り組みに緊張感も、目的意識ももたらしません。ただ、制限時間の設定の仕方は、お子様の様子によってそれぞれです。一律で「何分」と言えるものではないので、状況と目的に応じて塾サイドと相談をしながら取り組みたいところです。
- その「制限時間」の中では、立ち上がらない、話しかけない、話さない、スマホ見ない、などなど、「試験と同じ環境」で集中して取り組もう
→これは超重要で、ご家庭の協力も必要です。読解問題を取り組み始めたら、その制限時間の中では、絶対に「集中」させて欲しいのです。トイレもダメです。先に行かせましょう。立ち上がること、言葉を発すること、何か別なことをすること、全てNGです。この20分だけ、取り掛かり始めたら、必ず一息でやることが大事です。
緊張感のない読解問題演習は、基本的には価値がありません。試験を目的とした問題演習なのですから、常に「制限」と「緊張感」を持った練習にすべきです。野球で、部内の紅白戦は、本番と同じような緊張感で取り組むのと同じです。
ただ、ここが、小学生の子どもたちにとっては実に難しいです。塾の中ではしっかりやっている(やらざるを得ない)子達も、お家では、「のんびりと」読解問題をやっていることが多いです。でも、それではいけません。たった20分、30分の問題演習の時間です。この時間だけは、全力の集中モードで取り組みましょう!
- 取り組み終わったら、問題文の内容を確認しよう。内容が確実に理解をできているか、内容の深掘りをしよう
→ここが、実は、「読解力」をつけるためには最も重要な部分であり、なかなかご家庭や本人だけでは取り組めない部分だろうと思っております。いくつか事例を見てみましょう。
現行の予習シリーズの4年生の演習問題集の中に「ホタルはなぜ光るのか」という内容についての説明文があります。
化学反応について、発熱反応と、発光反応があり、そのうち、ホタルの体内で起こる反応は、光になる効率がいいので熱くならないことや、ルシフェリンとルシフェラーゼ(触媒)が混ざると光ることなどが書かれていますが、当然に小学4年生には、化学反応についての知識などないので、問題は優しいかもしれませんが、本質的には書いてあることの意味が分かりにくいです。
ただ、子どもたちは、読解問題を取り組むにあたり、この文章を真剣に読んでいます。
普通、小4で、化学反応についての説明文を読むような子はいません。しかし、読解問題を取り組む際は、真剣に、とても一生懸命読んでくれます。
ですから、この経験を無駄にしたくないのです。普段読まないような文を一生懸命読んだ。
そこで、できれば、この文章について、一緒に内容をまとめて、話を深掘りしてみて欲しいのです。
化学反応とはどういうものなのか。(発光反応と発熱反応、あるいは吸熱反応などの違い)触媒というのはどういう働きで、身近なものではどんなものがあるのか?(二酸化マンガンなどが理科ですでに出ているかもしれません)場合によっては、ホタルのルシフェリンとルシフェラーゼの化学反応式などを見せながら、それがオキシルシフェリンとなることなどを見せて、その「オキシ」が何であるのか、、などなどを話してみてもいいでしょう。そして、発光する生物にはどんなものがあるのか?
そんなことを一緒に確認すると、子どもたちは、その文章そのものにとても興味をってくれやすくなります。
このようなことができると、読解問題演習のために文章を読むということが、その経験が自分の「知識」になり「経験」になり、場合によっては、自分の「関心事項」へと変わっていきます。
大事なのはここだと思っています。
読解問題の演習をして、そこで読んだことを、自分の知識、経験に昇華していけるか、少しでも自分の中に取り込めるか。これができれば、読めば読むほど、その子の知識見識は広がります。
これが、普段の読書では、なかなかそうはいきませんし、それを求める必要はないです。なぜならば、読書は、自分のための、自分の楽しみのためでいいのです。そうあるべきです。リラックスして読んでくれればいいのです。
しかし、読解問題の際は、誰もが「真剣」に文章を読みます。どの機会よりも「書いてある内容が頭に入りやすい」状態です。ここを活かさない手はないと思うのです。
もう一つ別の事例も。
同じく予習シリーズの5年上巻10回に、豊島ミホさんが書いた、キレキレの女子同士の友情についてのお話が出てきます。高校生女子二人の、容姿などを含めた、学校内カーストの立ち位置の話、男子からの目線に対してのその反応、女子同士ならではの展開のお話で、彼女のキレの一端を感じられる、みずみずしい場面です。
でも、そんな高校生女子の「心情」を、小学校5年生の男子が「知っている」わけはないのです。体験したことも、想像したこともないでしょう。
もちろん、設問を解くということになれば、高校生女子特有の問題など知らなくとも解けるのですが、でも、せっかく、いい場面なのです、いい展開なのです。ここで、一生懸命読んだその内容、深掘りして、小5男子にも「擬似体験」をして欲しいのです。
こんな場面では、高校生女子たちには、こんな常識があって、こんなことを考えるものなのだということを。
小5男子は、自分から、女子高生の恋愛話の小説は手にしないでしょう。それでいいのです。でも、今、読解問題のためとはいえ、せっかく読んだならば、その体験を「知識」や「擬似経験」にしていきたいです。
もし、それができたならば、1つ、彼らの頭の中に、「女子高生の生態」についての経験がインプットされたことになります。
そうして、文章問題を解いていくたびに、新しい経験、新しい知識が吸収されていけば、問題練習をするたびに、どんどんと「読解力」がついていくことになります。
読解力とは、文章に書いてあることを、正しく理解する力です。それを構成する要素は、そんなに難しいことではなくて、語彙力と、なんといっても「似たような文章を読んだ経験」が大きな要素になります。
読解問題において、最大のアドバンテージは「その文章読んだことがある」であり、あるいは「扱われている話題を知っている」ことです。
例えば、野球少年を題材にした話は多いわけですが、昨今の少年少女たちは、野球のルールを知らないし、そもそも、高校野球やセ・リーグ、パ・リーグすらよく知らない子が大半です。そういう野球について無知の子達と、一方で、野球をやっている子では、後者の子たちには、ものすごく身近な内容で、読みやすい内容になるはずです。
そういう、自分にとって「知っている」領域をいかに増やせるか。
繰り返しますが、「そのために」本を読ませるというのは、本末転倒です。読書は、人生において、もっともっと大切な、大事な営みです。
しかし、読書によらずとも、読了の経験値はどんどん高めていくことができます。その最大の機会が「問題練習をした際の、その問題文から何を吸収するか」です。
ここができるのかどうかでは、問題練習の「成果」は質がまるで違ってまいります。
- 答え合わせは「すぐ」取り組もう
もしも、国語の問題を取り組んだ後、「終わった終わった」と席を離れ、答え合わせをしないままでいるならば、それはもう、とてつもなくもったいないです。
問題に取り組んだならば、「すぐ」に、答え合わせをしましょう。問題を解いた直後は、本文の内容も覚えていますし、問題を解いた「手応え」も確かな状態です。難しかった、やりやすかった、あそこの問題は迷った、ここの記述は自信がある、などなど。
答え合わせは、その手触りが残っている状態にすべきです。後でやってはいけません。なぜならば、時間を空けてしまうと、本文内容も忘れ、問題に対しての手触りもなくなるからです。
子供達は、問題練習を「問題を解く練習だ」と思っている子が大半ですが、違います。
問題練習は「自分が賢くなるために」やるものです。賢くなるには「できない問題」が「できるようになる」ことが絶対に必要です。ですから、問題を解いて「から」が、本当の勉強なのです。
これは、国語だけではないですね。実に、多くの子が、ここを勘違いしています。
問題を解いたら、すぐに答え合わせをして、できている問題、できていない問題、をしっかり色分けすることが必須です。
- 解説をしっかり読み込もう
答え合わせをして、正解と不正解が明確になったら、さあ、そこからが本当の「勉強」です。
間違った問題に対して、解説部分を「じっくり」「入念に」読み込んでいきましょう。その際には、問題文と、設問もしっかりと開いて、見比べながら取り組んでいきましょう。
その結果「ああ、そうだったのか、そこが考え違いだったのか」であったり、「この選択肢は、そこが本文と合っていないか、、」、あるいは「記述は、このポイントが触れられていないか、、」などなど。
そうして、「納得」できたならば、ようやく「できなかった問題ができるようになった」といっていいでしょう。
問題に対しての対応力が上がっていくのは、この「できない問題ができるようになった」という経験値が溜まっていくこと、このプロセスをたくさん積んでいくことが必要です。
逆にいえば、問題を解いて、この過程を経なければ、「できない問題ができるようになっていない」のですから、「その問題練習には、ほとんど意味がない」ということになります。その「意味がない」問題練習を、どれだけ積んだところで、残念ながら、読解問題への対応力、得点力は上がっていきません。
- もう一度、本文を読んでみよう
さあ、ここまできたならば、もう1つ。画竜点睛に当たる部分まで取り組みましょう。
子供達は、白地の状態から、文章を読み問題を解きました。今、本文の内容を深掘りし、さらに、答え合わせから解説を読み、スタート段階から比べれば、その文章に対する理解は、大いに高まっています。
この状態で、もう一度、本文を読んでみて欲しいのです。さっとでいいです。問題をやる必要はないです。本文を読むだけでいいです。
最初に読んだときに比べて、内容が頭に入りやすくなり、読みやすくなっていることを、確実に実感できはずです。これが、「読解力がました」という実感です。
この5分。この最後のたった5分を、是非とも取り組んでみて欲しいです。雲泥の差が生まれます。
