【読解力を作り出す】7)読解力をつけることが先。設問への対応力は後。
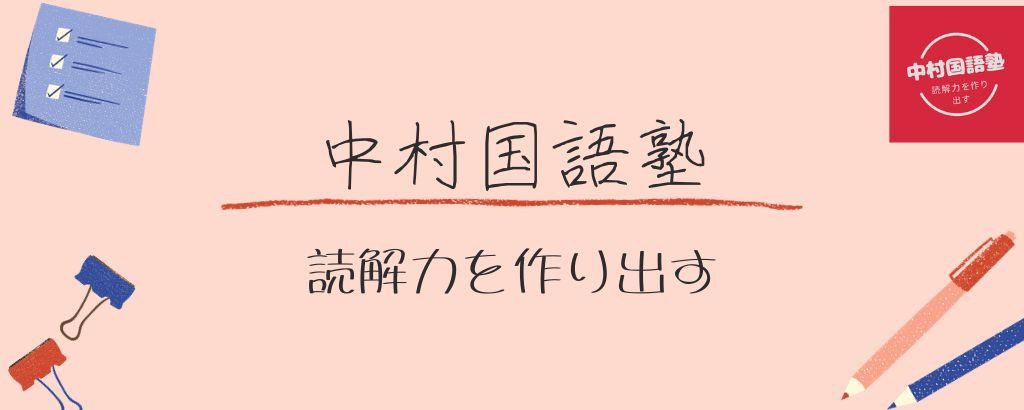
これまでは、読解力を高めていくことの重要性や、そのためのポイントを考察してまいりましたが、ここでははもう1つの大きなテーマである「読解問題を解く力=設問対応力」について考えてみたいと思います。
1)読解力をつけることが先。設問への対応力は後。
このテーマにおいて、声を大にして言いたいのは、本質的には、「国語の読解問題ができるかどうかなど、さして重要ではない」ということです。大事なのは、どこまで行っても「文章を読んで、内容が理解できているか、その度合いを高めること」だけです。
はっきり言えば、選択肢が選べようが選べまいが、抜き出しができようができまいが、そんなことよりも、文章内容をしっかり読めているかどうか、そちらの方が格段に重要です。
また、詰まるところ、どこまで行っても、「問題文の内容が読み取れている」ならば、その後の問題への対応というのは、「テクニックやスキル」に頼る部分は極めて小さくて済みます。だって「内容が読めている」のですから。
ですから、本来ならば、国語のテスト問題は、「課題文を読んで」それを「要約する」だけでいいと思うのです。あるいは、小説ならば、「場面や心情の解釈をする」だけで。それを見れば、その文章を理解できているのか、そうでないのかは十分に把握できるはずです。
でも、現実は、入試ということについて言えば、これはなかなかそうはいかないです。しっかり「明確な基準」で「得点による序列」をつける必要があるので、どうしても、「正解か不正解か」という問題を作ることになります。
それゆえに、その「設問に対応する力」というのがクローズアップされるわけです。
しかし、繰り返しになりますが、読解力というのは、本質的に設問に対応する力とは別物です。いくら設問に対応する力をつけても、文章を読んで理解できなければ、何の意味もありません。ですから、あくまで「読解力をつける」ことが先であり、「設問への対応力をつける」ことは、その後です。ここを、絶対に間違わないように。読解力がついていない段階で、設問への対応力を上げることばかりやっていても、本質的な読解力は身につかないし、それどころか、読んだ内容の理解について、正解か不正解か、択一的な基準で評価をしてしまうと、「読むこと自体がどんどん嫌いになっていく」ことになりかねません。
極論、読解力をさえつければ、国語の問題など、概ねなんとかなります。しかし、その逆はありません。しかしながら、多くの中学受験の指導で、読解力をつけるアプローチを蔑ろにしながら、設問を対応する力ばかりに傾倒しているきらいがあり、これは、受験指導の大きな大きな弊害の1つだと思っております。
2)設問対応力が占めるウエイトは2割もない
さて、そのような前提をベースにて、では設問への対応力については、どう考えていけばいいか。
僕は、読解力をつけるための取り組みと、設問への対応力をつける工程の比率は、前者が8割、後者が2割程度でいいと思っております。なんでしたら、受験学年になるまでは、設問への対応力など特段アプローチしなくても良いのではないかと思っております。
なぜか。
実は、国語の設問の形式というのは、そんなたくさんの種類があるわけではないです。具体的にみますと、
- 接続詞を選ぶ
- 言葉の意味を選ぶ
- 空欄補充
- 内容についての選択肢
- 内容についての記述
- 本文からの抜き出し
- 段落わけ
- 欠文補充
- 指示語の内容を問う
- 表現技法、敬語や、文法の用法を問う
このくらいで、全体の9割以上を占めるのではないでしょうか。
繰り返しですが、これらの内容について、「本文が理解できて」いるならば、問題への対応は容易です。が、「本文が理解できていない」でこれらの項目を、テクニカルに対応することは、できないとは言いませんが、それはなかなか大変ですし、それができて、試験で点になる以外に、一体何になるのか、、という感があります。
これらの代表的な設問方式については、確かに対応のためのテクニカルな有効な方策があります。それらは実にたくさんのアプローチの技法があります。どれも素晴らしいものばかりです。次回以降に、いくつか、私たちの考えも記載したいと思います。
しかし、それでも、どこまで行っても、「たった」これだけです。数学やら理科とは違うのです。持つべき解法のセオリーは、多くとも10数個です。もちろん、それらの技能は「レベル」があるので、初心者レベルから、どんどんと使い手のレベルを上げていくことで、精度が高まります。
「設問対応力を上げることが」「読解力の向上につながる」というのは幻想です。設問対応力は、あくまで「読解力がベース」に、その上に作用するものです。
