【読解力を作り出す】8)選択肢問題より記述問題の方が簡単!
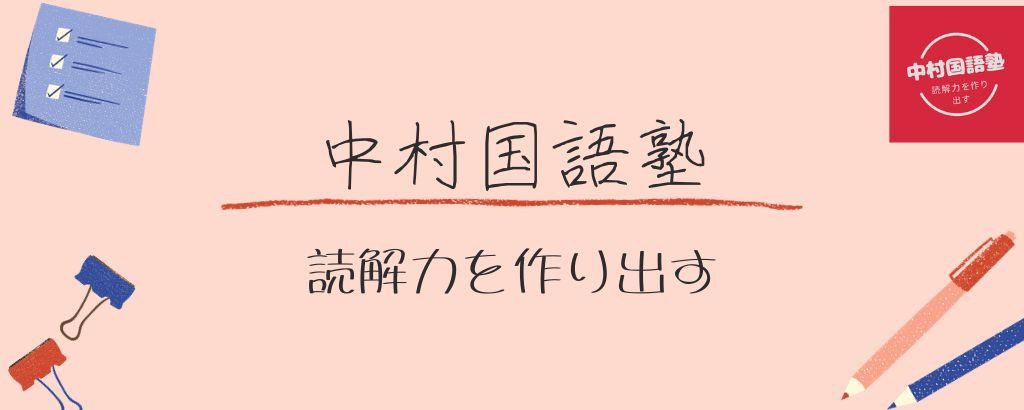
国語の指導をしていると、いちばん多くいただく相談は「選択肢の問題は対応できるのですが、記述の問題が難しくて・・」というものです。現実、小学生や中学生の答案において、記号は書かれているけれど、記述問題は白紙状態という答案は多いです。
しかし、本当に、記述問題は、選択肢の問題よりも難しいのでしょうか? この章では、この疑問を検証していきたいと思います。
1)2つの問題を比べてみよう
小学5年生の予習シリーズの下巻の「演習問題 6回」に、佐藤多佳子さんの「サマータイム」が引用されている文章題があります。
片手が不自由な広一くんと、エキセントリックな姉と、5年生の僕。夏の終わり3人で姉の作った「砂糖と塩を間違ってしまったゼリー」を食べた時の場面です。その、衝撃的にまずいであろうゼリーを食べた広一くんが言った言葉 -「あ、海だ!」に3人が3人、それぞれの反応をします。
なかなか独特な場面で、夏の終わりの寂しさ、無理に食べるしょっぱいゼリー、汗と塩、海の色とゼリーの色。姉のキャラと広一のキャラクターの化学反応。3人で囲む食卓に起こっている様子をイメージして味わいたい場面です。
情報不足ではありますが、この場面に対しての2つの設問を見てみてましょう。
問 僕は「あ、海だ!」と言った広一の言葉に「すごい」と思いました。その理由を選んでください。
ア)広一くんが、佳奈が塩と砂糖を間違ったことで起こるであろう争いを、機転を聞かせて話題を変えたことに感心したから
イ)ゼリーを海に例えることによって、間違って塩を入れてしまったことを認めない佳奈の嘘を暴いたことに脱帽したから
ウ)中に入っているのが砂糖だろうが塩だろうが関係なく、見た目だけの印象でものを言う広一くんに驚いたから
エ)間違って塩を入れたゼリーが、見た目だけでなく完璧な「海」だと思った広一くんの感性に感嘆したから
選択肢は筆者がアレンジしております。
なかなか難しいですよね。どれもいいような気もしますが、どれかを選ばないといけません。
この場面と、その後の展開を見ると、ア)話題を変えた、とはいえず、 イ)の佳奈の嘘を暴いた、と言う印象だと、この後の割とフレンドリーな展開には似つかわしくないです ウ)広一くんが「見た目だけで」ものを言ったかどうかは変わらないし、塩味を感じてのことですから、おそらくこれは違うでしょう。そのように考えて、エ)を残すべき問題ですが、時間が限られているとなかなか吟味は難しいです。
他方で、こちらの問題を見てください。
問 僕は「あ、海だ!」と言った広一の言葉に「すごい」と思いました。その理由を30字以内で書いてください
同じ問題で、選択肢がなくなり「「「30字で自分の言葉で書きなさい」と言う問題に変わっています。
この時に、この選択肢の問題ならば何かを選べますが、記述だと白紙にしてしまうケースが多いわけです。「難しい」と思い。
確かに簡単ではないです。でも、この2つの問題を考えるにあたって、考えるべき内容は基本的に同じです。同じ場面の、同じ問題なのですから。
要素としては、以下のようなことが挙げられるでしょうか。
- 僕は、広一くんの言葉に対して「ポジティブ」な思いか「ネガティブ」な気持ちか
- すごい、と感じる原因となる事象を認識できるか
- 広一くんが佳奈をどう思っているか。好意的か、敵対的か
このくらいでしょうか。
1に対しては、「ポジティブ」と読み取れているでしょう。多くのケースで。2も簡単です。直前に、甘いはずのゼリーが、砂糖と塩を佳奈が間違ったことで、しょっぱくなっていることが書いてあります。それに対して、佳奈は「間違えていない」と言う滅茶苦茶な言い訳をします。言い争い、喧嘩になりそうなところです。3は、この後を読むと、基本的には、佳奈に対して好意的な思いでいることがわかります。
もしも、この3つについての「読解」ができているならば、この時の僕の気持ちを30字で書くことは、そんなに難しいことではないでしょう。
広一の機転の効いた言葉によって、佳奈の大失敗が大惨事にならなくて済んだわけです。
この事実を30字で書き出せばいいのです。5点満点の問題ならば、多少文章に違いや、表現の手違いがあっても、大筋を外さなければ、悪くても3点以上は取れそうなものです。
しかし、選択肢の問題ならば、このように読み取れていても、ア)とエ)は結構迷いどころです。「話題を変えた」と言う言葉をしっかり否定できないと、ア)を切りにくいです。時間制限のある中では、読み取れていてもア)を選んでしまう可能性は十分にあります。
そうすると、この5点問題は0点になってしまいます。
大事なことは、「どちらも、同じように読解できているのに、選択肢問題は0点になる可能性があり、記述問題は悪くても3点である」と言うことです。
2)記述問題に必要な文章力は高くない
ある場面に対しての読解状況が等しいならば、選択肢問題と記述問題ならば、記述問題の方が得点できる可能性は高くなります。それでも記述を「難しい」と感じるのは、「文章で答えることに自信がない」と言うことがベースにあるのだろうと思います。
しかし、50字程度くらいまでの記述問題には、実は
「高い文章力など全く必要ない」
です。
ここを取り違えないようしたいです。文章力をつけると言うのは確かに長い道のりです。他の人が見て「上手だ」と思ってもらえるな文章を書くようになるには、これは相応のトレーニングが必要です。
しかしながら、国語の試験の記述問題へ解答する程度のことで、上手な文章が書ける必要などありません。ごく普通に、主語と述語がかけて、修飾被修飾の関係に誤りがなく、接続後が1つ2つ、適切に使えればそれでいいです。それだけのことです。(もちろん、このレベルの一文の作成が困難な場合は、それを練習する必要があります。ただ、そう言う場合は、読解力云々以前の状態であることが多いです)
ですから、先ほどの問題に対しての解答ならば、
佳奈が砂糖と塩を間違ったことを、上手に言いかえていることに感心したから。
(とある少年の解答そのまま)
で十分です。もしかしたらこの解答は満点ではないかもしれません。でも、5点中ならば4点は確実にもらえるでしょう。
この文章を書くのに、どんなスキルがいるかといえば、特別なスキルはいらないでしょう。文章を書くと言う点においては。
しかし、大事な視点が1つあります。このレベルの問題を白紙にしたいための大事なポイントが。
3)頭の中のイメージを、自由に文章化できるか
読解問題の多くの記述問題において必要なのは、その場面に対しての「読解力」であり、ごくごく標準的な「文章力」です。前者ができていなければ、記述だろうが選択肢だろうができない可能性が高いです。後者については、一般的な日本語の一文が作れない状態の子は、読解力云々の話ではないことが多いです。
では、どうして記述問題を白紙にしてしまいがちなのか。それは、
「自分の頭の中を言語化」
することに慣れていない子が多いからだと思っております。
場面の読解としては十分に認識できているとしましょう。でも、白紙になっている記述問題について、口頭で問答をしているとよくあるのが、「口で話せば話せる」と言う状態であることです。とても多いです。つまり、頭の中に、解答のイメージはあるのです。ある程度。しかし、それを文章によって言語化することに躊躇いがあるのです。あるいは、不安がある、怖さがあるのです。だから、口頭でやり取りをしていくと、するっと言葉になっていく。
「自分の頭の中のイメージを言語化する」このことを、しっかりトレーニングする必要があるのです。
どうやって言語化のトレーニングをするかについては、ここでは詳述は避けますが、単に「書く」と言ってもトレーニングの仕方はいろいろあります。特に、このトレーニングでは、「言語化」することが目的なので、細かい「てにをは」とか、文章が流暢であるかどうかとか、言葉遣いとかは重視しません。きちんと、頭の中で考えたこと、描いたことが、読み手に伝わる形で「文章にできているか」のみを問います。そして、そのスピードと分量を重視していきます。
繰り返しですが、自分の頭の中の「言語化」と言うのは、これからの子供達にとりとても重要なスキルになるだろうと思っています。私たちの頭の中は見えません。それを表現する方法は、口頭であったり、身振り手振りであったり、動画であったり、歌であったり絵であったりといろいろですが、その中でも 「文章で伝える」と言うことは、改めてメジャーな手段であろうと思います。その力を、小学校の時代に身につけていくと言うことは、国語の問題云々を別にして、非常に重要なものであろうと思っております。
