【読解力を作り出す】6)語彙の習得は2段階
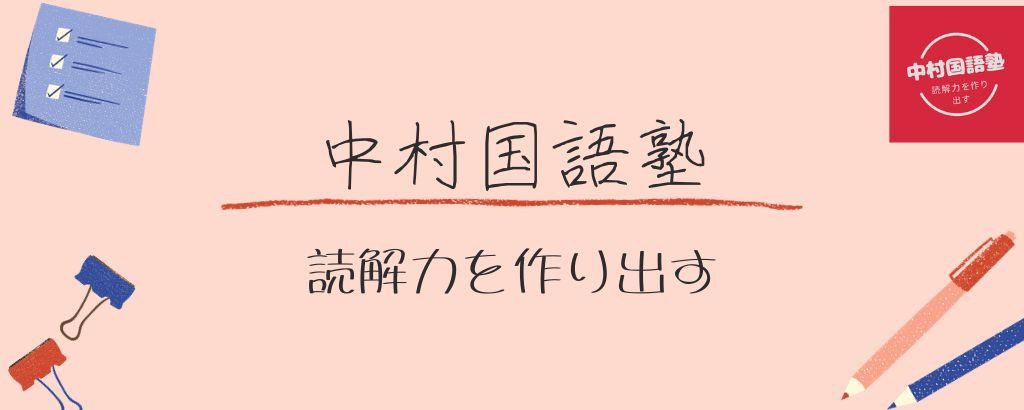
文章が読みづらいと感じる時の原因として、もっとも多いものは「書かれている言葉の意味がわからない」ということでしょう。
例えば、この文章の意味を、一読して理解できるでしょうか?
量子重力理論は、GRTとQMの統合を目指す理論物理学の最前線である。LQGは時空の離散的量子化を、弦理論は高次元統一理論を提供し、CDTやアシムトート安全重力は新たな視点をもたらす。しかし、実験的検証の困難さや理論的一意性の欠如により、完全な量子重力理論は未確立である。宇宙論的観測や量子情報理論の進展が、今後のブレークスルーを牽引する可能性が高い。
量子重力理論の課題について、AIにレポートを作ってもらったものです。
これ、普通の人は理解できないですよね? そもそも量子重力理論を知らないし、離散的量子化とか、弦理論、アシムトート安全重力、宇宙論的観測など、普通の人には馴染みのない言葉が連なっているので、ある種のお経のように感じます。
お経といえばこんな感じです。
私が仏となって以来、無量無辺の百千万億那由他の劫(無数の時間)が過ぎ去った。私は常に法を説き教え、無数の億の衆生を仏の道に導いてきた。それ以来、無量の劫の間、衆生のために方便として涅槃(死)を現じたが、実際には滅することなく、常にここに留まり、法を説き続けている。
如来寿量品第十六(にょらいじゅりょうほんだいじゅうろく)からの抜粋
わからない言葉が多すぎて、読んでいると眠くなります。
そうなんです。文書を読んでいて、知らない言葉が多いと、どういうわけか集中力を欠き眠くなります。何か科学的な理由があるのかもしれません。
いずれせよ、「知っている言葉を増やすこと」が、文章を読みやすくすることは間違い無いでしょう。
では、語彙力をつけていくためには、どのようなポイントがあるのでしょうか。ここでは、2つの「段階」に注目してみたいと思います。
1)幼少期から低学年にかけてはご家庭で
小さい頃、周りの大人たちから「よくこんな言葉知ってるね、すごいね!」と言われたことはありませんか? あるいは、そういう子、いませんか? 小学生低学年なのに、大人顔負けの熟語を使ったりする子ですね。一定数そういう子がいます。
これは、彼ら彼女たちが天才的ということも稀にあるかもしれませんし、英才教育の賜物ということもあるかもしれませんが、実際はそうではなくて、ほとんどが「親御さんの影響」です。
第一言語は、その修得段階においては、最も身近な人からの影響を受けます。つまりは、ほとんどの場合は親です。
そこで、イメージしてください。5歳の子を持つ親御さんAは、日々難しい言葉を使って話しかけてきます。
「わが子よ、君の日常には、ちょっと頑張りが足りないように感じるんだ。早く自分の目標を決めて、勉強に励んでほしいな。そうすれば、将来きっと成功できるよ。ところで、今日の夕食は何がいいかな?」
それに対して、親御さんBは、くだけた言葉を多用します。
「ねぇ、ちっちゃいヒーロー!お砂遊びパーティー、めっちゃ楽しかった?うひゃひゃ、キミのニコニコ顔、超カワイイぞ!ほいでさ、ご飯タイムだよ~、ナニナニ食べたい?モグモグしちゃおうぜ!」
これはかなり極端な表現ですが・・・どちらがいい悪いではないと思います。しかし、日々Aさんのような言葉に接している子どもと、日々Bさんのような言葉に接している子供では、習得する言葉に差が出るのは間違いありません。
子供は好奇心の塊です。親からかけられる言葉で、わからない言葉があればそれを聞いてくるはずです。「それ、なんていう意味?」と。その時に、「これは、____という意味だよ」と簡単でいいので伝えていくと、子供には「モデリング」という機能が備わっていますので、親の真似をして、その言葉を使ってみようとするものです。
こうして、「知らない言葉に触れる」ー>「意味を知る」ー>「使ってみる」というトレーニングが、ごくごく自然に、そして、子供にとっては「興味関心を持って、楽しく」取り組めているのが、幼少期から低学年のご家庭ではしばしばみられます。
テレビを一緒に見ていても、そこで使われる言葉に対して、興味を持った時に、すぐに「それは___だよ」と伝えると、その1つ1つが子供たちの中に蓄積されていきます。
それが日々続いていくと、それだけで、膨大な「言葉の知識」がストックされていき、一見大したことはしていないように見えて「よく言葉を知っている子」が形成されていきます。
この段階は、もちろん、意図的に取り組むことも十分可能です。子どもというのは、実にかなり多くの子が「言葉に対して意欲的」です。幼少期から低学年にかけては。ですから、意図的に難しい言葉を語りかけたり、意図的に、言葉に対しての質問を投げかけたりし続けることで、この年代の子どもたちは、驚くほど言葉を吸収して行きます。
2)小学生の中盤以降は、体系立てた学習が必要
親御さんからの働きかけで、低学年期の子どもは一気に豊かな語彙を備えていきますが、残念ながらそれだけでは語彙は「ある程度」までしか増えていきません。
それはそうです。
日常の会話で私たちが使う表現、言葉というのは、基本的には「話し言葉」であり、「書き言葉」ではありません。しかし、学習のかなり多くの部分は「書かれた文章」で行なっていきます。そこには、話し言葉とは違った種類の言葉多く使われていきます。
また、日常生活の中では、特定の話題についての深掘りは「ある分野」でしか起こらない可能性が高いです。例えば、生物について大好きな子は、生き物や生態についての言葉は詳しく知るかもしれませんが、歴史についての言葉はまるで興味がないので、触れることはないかもしれません。
でも、言葉というのは、特定の分野、特定の種類だけ、自分の好みによって習得していけばいいという類のものではありません。
例えば、とある5年生の国語の問題文で出てきた言葉に、
「一蹴」「杞憂」「暗黙」「邂逅」「齟齬」「遵法」「顕著」「拮抗」
という言葉が並んでいましたが、これらの言葉を、日常の会話の中で触れる可能性は、小学生にはほとんどないだろうと思います。
ですから、ある程度の年次以上になれば、言葉、語彙というのは「計画的に体系だてた学習が必要」です。
ここを勘違いして、幼少期から言葉の習得が早いし、大人びた言葉を使うので、、、と放っておくと、5年生くらいになると、一気に「文章が読めなく」なります。その理由は、「知らない言葉増えた」からです。しょうがないです、上記のような言葉は、「積極的に自ら学習」しないと身につくはずはありません。
概ね、4年生くらいからでいいでしょう。語彙力強化のための学習は。そして、これは、実に「簡単」であり、場合によっては「面白い」と思える学習です。特に、言葉をそれまでによく使ってきた子にとっては、新たな言葉が身につくというのは、充実感のある取り組みです。
順番としては、
- 2字熟語、和語などのいわゆる「語彙」の学習
- 外来語などのカタカナ文字の学習
- ことわざ、四字熟語、慣用句、故事成語など、特殊な用語の学習
- 一般教養的の学習
というようなところになるかと思います。それぞれに対して、対応する冊子を「1冊」取り組んでいければいいと思います。2は、そもそも1とくっついていることも多いでしょう。
4の一般教養の学習は、イメージはこんな冊子です。
例えば、西洋音楽の父といえばバッハというのは、ある種の「常識」でしょう。世界共通の。そういう、一般教養にあたる知識というのは、実に文章の中では「当たり前のこと」として使われ、いちいちそれについての解説や説明はされません。パスカルが「人間は考える一本の葦である」といった人であり、hPaのパスカルでもあることなどは、「誰でも知っている」ことであり、小学生も高学年ならば、知っているべきことでしょう。
日本の学習は、基礎学力についての習得については秀逸ですが、いわゆる一般教養的なことについては、少しおざなりな感がありますので、こういうところはしっかり補強をしておきたいところです。
