【読解力を作り出す】5)漢字は「前提条件」
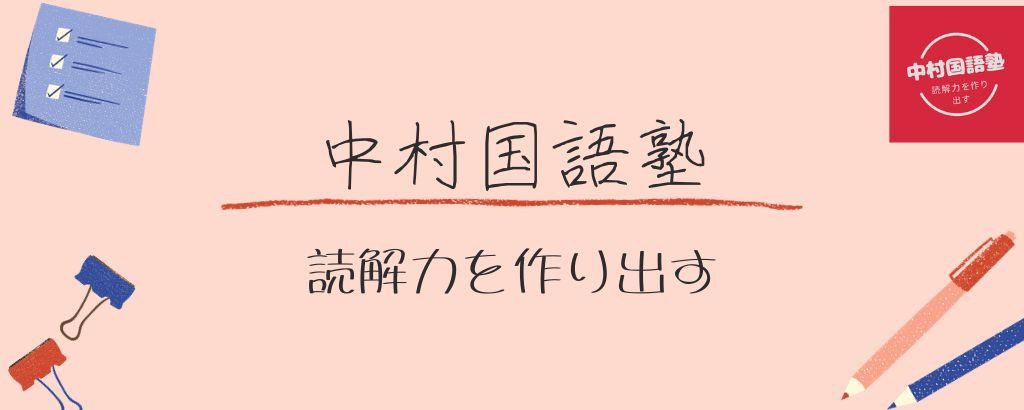
読解力を考える際に、1つの大きなテーマになるのが「漢字の学習」です。漢字は小学校で1026文字、中学校ではさらに1100文字習い、合計2136文字が「常用漢字」として指定されております。
この漢字の学習と読解力をの関係性を考えてみたいと思います。
1)漢字習得のポイントは小学2年生から4年生
漢字学習は、1年生の段階では80文字に限定されますので、そこまで話題に上がることがありませんが、2年生になるといきなり倍増の160文字、3、4年生では1年間で200字以上を学習することになります。この2−4年生が、漢字習得においては重要な期間になります。
多くの学校では、2年生以降になると、毎日のように漢字の宿題が出されます。多くのケースが、1漢字について「漢字学習帳」に1ページ程度の練習量が課され、さらに漢字ドリルの取り組みが加わります。ノート1ページへの漢字の練習はなかなかの分量で、これをしっかりやり切っていけば、ある程度漢字の学習は形になるはずです。
でも、ここが結構大変ですよね。。200文字となれば、学校が年間40週程度とするならば、ほぼ「毎日」取り組まないといけません。習い事もあれば、体調の問題もあるでしょう。運動会などのイベントが入ってくれば、さらに忙しくなります。そういう中で、ほぼ毎日欠かさず漢字の練習をしていくというのは、大変なタスクです。
故に、どうしても、この2−4年生の期間で、漢字の学習には差がつきがちになります。
漢字の練習を、1日で4、5ページもやるというのはとても苦しい作業です。1日1、2ページ程度くらいまでが、普通は集中しながらできる限界でしょう。ですから、漢字の習得というのは、極めて
学習が習慣化されているかどうか
という点とリンクします。
つまり、毎日15分ー20分程度かかるこの漢字の学習を、コツコツとこなせるような学習習慣になっているご家庭では、漢字の学習は、ある意味ルーティーンとなり、着々と進んでいきます。1つ1つの作業も集中して、端的に取り組めることが多いでしょう。他方で、そのような習慣がないと、漢字の練習を「貯めて」しまうことになり、そうなってしまうと、いきなり「漢字6文字分、6ページ」と言われれば、げんなりしてしまい、覚えるというよりも、「やればいい」というスタンスになりがちです。
そうなってしまうと、せっかく時間をかけて漢字を練習しても、漢字を習得しきれないことが多くなります。
もちろん、漢字の習得がこの1点とのみリンクしているわけではないですが、是非とも「漢字の学習を通じて、学習の習慣化を図る」ことを、2−4年の中では是非とも取り組んでほしいです。
この2−4年生で習う562文字、ここの習熟度合いが、読解力に対して大きな影響を持ちます。
2)80%の習得率ではだめ!
例えば、いくつか事例を見てみましょう。
2年生で習う漢字の習得率が80%だとします。その場合は、32個の漢字が認識できないとします。
32個ですから、
「南 肉 馬 売 買 麦 半 番 父 風 分 聞 米 歩 母 方 北 毎 妹 万 引 羽 雲 園 遠 黄 何 夏 家 歌 画 回 」
がわからないとします。(無作為に選びました)
実は、この32文字が書けないと、3年生で習う漢字の、多くが「書けない」「読めない」状態になります。
例えば、「速」という漢字を習う際に、風速(2年+3年)という熟語を練習するのですが、この「風(2年)」が書けない、読めない状態だと、練習がままなりません。
図画(図+画)、家族(家+族)、肉球(肉+球) などなど。
2年生の漢字の出来具合が80%ならば、3年生以降の漢字の学習の際に、「2年生の漢字が書けない、読めないから、3年生の漢字が使えない」ということになる可能性が、20%もあることになります。
つまり、漢字の積み残しが1年で20%あれば、読めない、書けない漢字が毎年20%ずつ増えていきます。2−4年でその状態を続けると、100文字が書けない=その漢字を使う熟語、数百語が読めないということになります。
読めない漢字は、ほとんどのケースで「意味がわからない」状態です。読めない、意味のわからない状態が、増えれば増えるほど、文章の読解に対して影響が出るのは必定です。
小学生の漢字学習は、
100%を期す
という覚悟をしっかり持ちたいです。90%ではダメです。100%を常に目指し、結果的に90%台の習得ならばしょうがないでしょう。しかし、とにかく「100%マスター」がデフォルト、という意識を、親子でしっかりと持ちたいところです!
3)漢字練習の際に注意したい、たった1つのこと
漢字の学習を進める際には、書き順や、音読み・訓読み、部首や造り、送り仮名など、注意したい点があれこれありますが、なんといっても一番大事にしたいのは、この1点です。
書いている言葉の意味を認識しているか
以下は、あるご家庭との面談時のお話です。
3年生のA君は、学校からの宿題で「図」という漢字を練習しています。漢字を何回か書いた後、自分で熟語を調べて5個ずつ書く練習があり、辞典を使って調べて書いていきます。
”企図”
”図画”
という漢字を書いているのですが、ふと気になって
「企図ってどういう意味?」
と聞いてみると、
「知らない」
と一言。
「え、じゃあ、図画は?」
「図工の授業のことでしょ」
とのこと。
その後、他のページで書いている熟語の意味を聞いてみると、8割がた、正しい意味を知らずに、ただ書いているだけでした。。
漢字がなかなか書けるようにならないケースの多くに、このように「意味をわからない言葉をただ書いている」ということが見られます。
英単語のスペルを学習するときに、「綴りだけ」学習することは絶対にありません。それは、単なるアルファベットの羅列になってしまい、意味のない「記号」になってしまうからです。必ず、綴りと意味、をセットで学習します。
漢字の学習も同様です。漢字を書いているけれど、その意味を認識していないというのは、言葉の練習ではなくて、複雑な暗号記号の習得のようなものです。
ここを掛け違えているケースが実に多いです。意味のわからない文字を、ただ書いていても、言葉の学習にはならない、つまり、身につくことはありません。(スペルだけわかって、意味のわからない単語は、絶対に使えません)
漢字の学習は、漢字の学習が目的ではなく「言葉の習得」が目的です。言葉には必ず「意味」があります。その意味を知らずに漢字を書き連ねても、それは、なんの意味もありません。
漢字の練習をするときは、その言葉の「意味」を必ず確認すること!
この1点だけは、絶対に逃さずに漢字練習をしてほしいです。これをしないと、どれだけ漢字を練習しても、漢字を「使える」ようになりません。
